遺族年金ってなあに?
これまで「老齢年金」「障害年金」について学んできました。
今回は、家族を亡くしたときに残された人を支えてくれる制度、
「遺族年金(いぞくねんきん)」 について説明します。
遺族年金とは?
遺族年金とは、家族を支えていた人が亡くなったとき、残された家族に支給される年金です。
働き手を失って収入が減ってしまう家庭を、国が支える目的で作られています。
つまり、「もしものとき」に家族の生活を守るための制度です。
対象になる人は?
遺族年金を受け取れるのは、主に亡くなった人に扶養されていた家族です。
対象となるのは、次のような人たちです。
| 対象 | 主な条件 |
|---|---|
| 配偶者(夫または妻) | 結婚していて生計を共にしていたこと |
| 子ども | 18歳到達年度の3月31日まで(または障害のある子) |
| 父母・孫・祖父母 | 配偶者や子がいない場合など、条件を満たすとき |
特に多いのは、夫が亡くなって妻と子どもが受け取るケースです。
ただし、最近では逆に妻が亡くなって夫が受け取るケースも増えています。
遺族年金の種類
遺族年金は、加入していた制度によって2つの種類に分かれます。
- 遺族基礎年金(国民年金)
国民年金に加入していた人が亡くなった場合に支給されます。
対象は「子のある配偶者」または「子ども」です。
支給額(2024年度)
約78万円+子の加算
(第1子・第2子は各約22万円、第3子以降は各約7万円)
- 遺族厚生年金(厚生年金)
厚生年金に加入していた人が亡くなった場合に支給されます。
受け取れるのは主に「配偶者」や「子ども」です。
支給額は、亡くなった方の給与・加入期間によって変わります。
受け取れる条件
遺族年金をもらうためには、亡くなった方が次のどれかを満たしている必要があります。
- 国民年金や厚生年金の加入中に亡くなった
- 過去に保険料をきちんと納めていた
- 障害年金を受け取っていた
つまり、「年金にきちんと加入・納付していたかどうか」が重要なポイントになります。
遺族年金はどのくらい続くの?
子どもがいる場合、子どもが18歳になる年度の3月までが基本です。
配偶者が受け取る場合は、一生涯ではなく、一定の条件のもとで支給される仕組みです。
また、妻が40歳以上で子どもがいない場合など、
「中高齢寡婦加算(ちゅうこうれいかふかさん)」という特例が追加されることもあります。
まとめ
遺族年金は、家族を失ったときに「生活の安心」を守る大切な制度です。
- 亡くなった人の年金加入状況によって支給される
- 残された家族(配偶者・子どもなど)が対象
- 加入制度に応じて「基礎年金」と「厚生年金」がある
「まさか」のときに備えるためにも、
自分や家族の年金加入状況を確認しておくことが大切です。
次回は、これまでの3つの年金制度をまとめて、
「年金制度の全体像と見直しのポイント」をお伝えします。

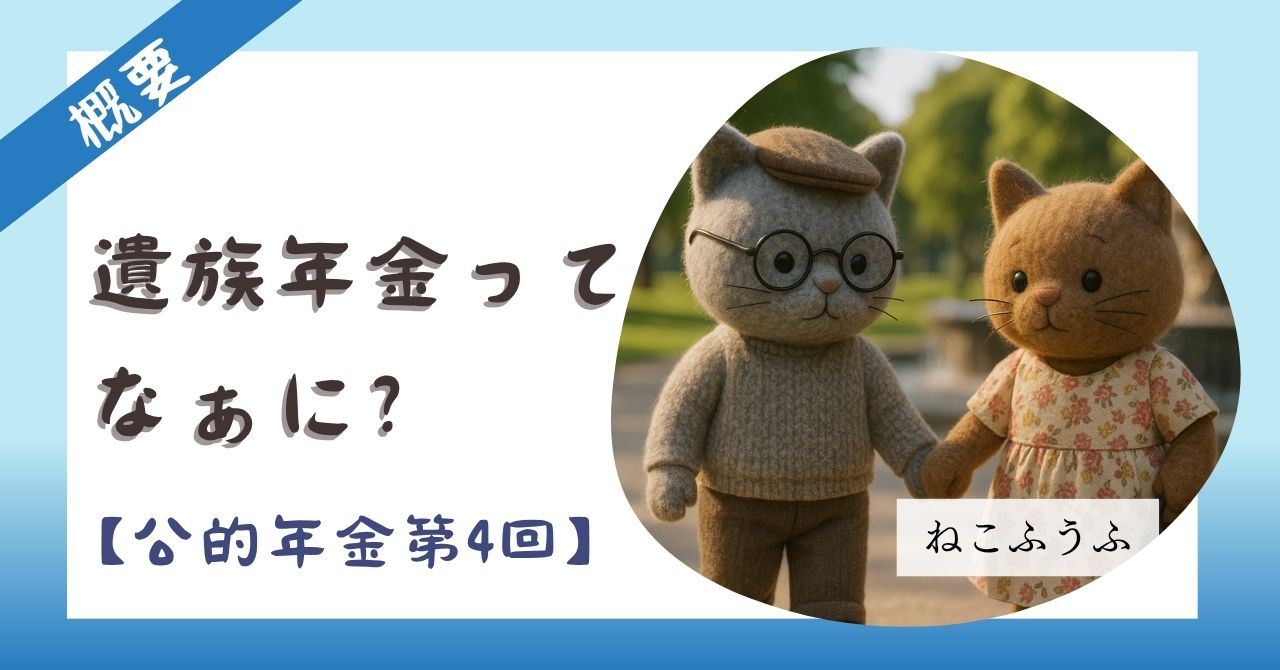
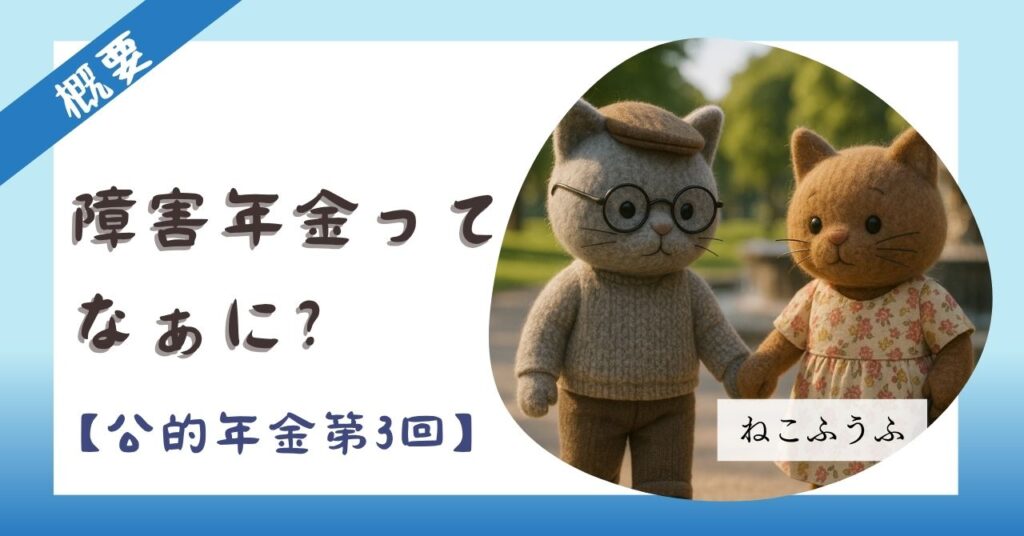

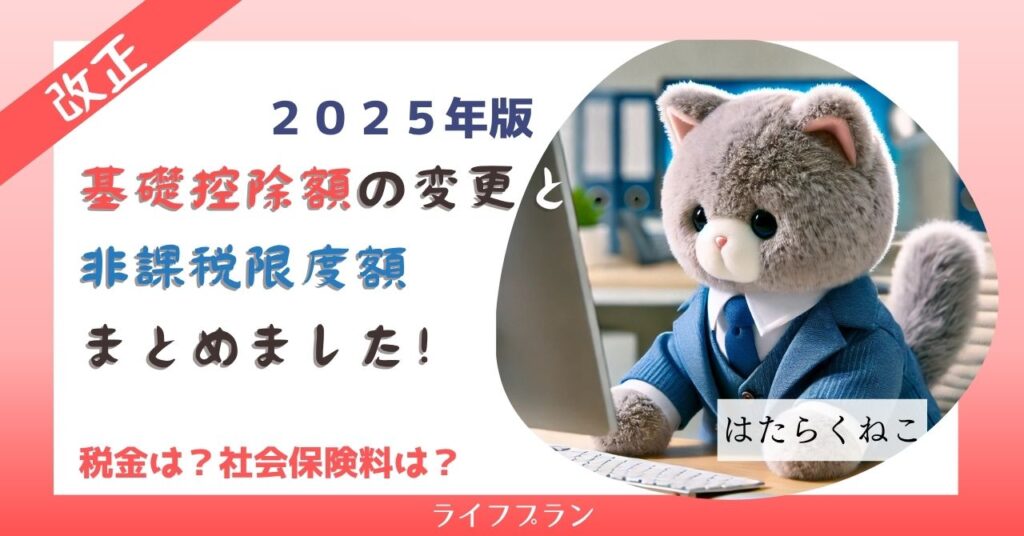
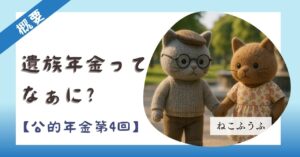

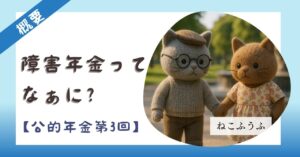
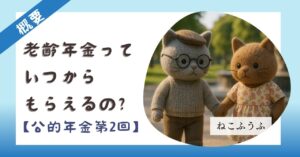
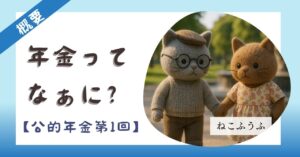
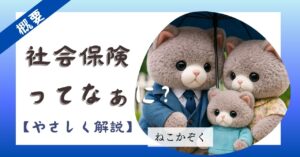
コメント